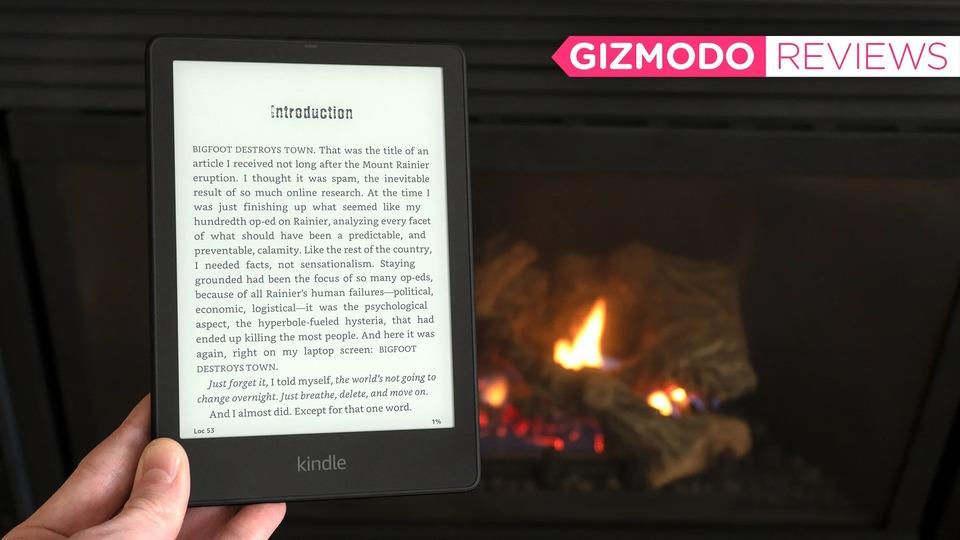90年代なかば、カシオのデジカメ「QV-10」を使っていた頃。25万画素! では、画像が粗すぎてとても取材には使えない。ちょっとした立体スキャナ、画像メモの位置づけだった。外出先でQV-10しか持っていないとき、とてもいい風景に出会って思った。「ああ、フィルムカメラで撮ればよかった」。やむを得ずQV-10で撮った写真は、その風景がどこを撮ったものかすらわからないほどのできばえ。実用になるのはまだフィルムカメラしかなかった時代だ。 時は流れ、一般的なデジカメが1000万画素近くまで高画素数化が進んだ頃、フィルムカメラは徐々に駆逐されていった。たまたまフィルムカメラを持ち歩いていて、いい風景に出会ったときに思った。「ああ。デジカメで撮ればよかった」。フィルムカメラはお金がかかる。フィルムの購入に始まり、現像、引き延ばし。さらに、デジタル環境に適合させるため、デジタル化するためのスキャナも必要だった。デジカメで画質が遜色ないとなれば、フィルムカメラの存在意義は小さくなる。今やフィルムカメラは、一部の好事家が使う撮影機材へと変わった。デジカメが取って代わるのは歴史の必然だった。半世紀以上を生きてきた私は、フィルムカメラで写真をおぼえた正真正銘のカメラ世代。フィルムからデジタルに乗り換えたとはいえ、口が裂けても一眼レフよりスマホのほうが良く写るとは言いたくない。内心、スマホで撮った写真のほうが多少良く写っているように思えても「ディテールはデジカメの圧勝だ」と自分に言い聞かせる。カメラやレンズに一体いくら投資してきたと思ってるんだ。そんな歴史と機材の重みに、尻ポケットに入れると折れてしまいそうなスマホが勝てるはずがないじゃないか。 一眼レフなら、うまくいけばきれいでいい写真が撮れる。うまくいけば。しかし、少なからず、失敗する。ピントが合っていない。ぶれている。カラーバランスが転んでしまった。明るすぎた。暗すぎた。もともと写真はそんなものだった。失敗を経験し乗り越えて身につけられる技術が撮影術だった。ところが今や、ピント位置は後から変えられる。ほぼ真っ暗な状態でもそれなりの画質で撮影できる。AI(人工知能)が状況を判断して適切な絞りとシャッタースピードと感度とカラーバランスを選んでくれる。ライティングも調整し、プロ顔負けのポートレートも撮れる。シャッターチャンスすら、AIが判断してくれる。そんな時代だ。スマホなら。最初に紹介した若手記者の言葉は、そんな時代を象徴しているのだ。 中国のスマホメーカー、ファーウェイのプレゼンがぶっ飛んでいた。将来、見えないモノを撮れる技術が開発されるという。例えば光子撮影技術。車や人体の内部構造が撮れたり、曲がり角の向こう側の画像が撮れたりするようになる、そんな内容だった。上海で開かれた「CES ASIA 2018」の基調講演でのことだ。さすが、自らAI機能搭載のCPUを開発し、スマホに搭載してしまった企業だけのことはある。スマホにカメラユニットを2つ搭載して、撮影後もピントを再調整できる機能を搭載したのも、同社が最初だった。かなり大きな風呂敷とはいえ、見えないモノを撮る技術も、実現不可能とは言い切れないだろう。そのとき、カメラはまだ生き残っているのか……。フィルムカメラのように好事家の道具として細々と生き残ることになるのか……。それとも消えてしまうのか……。カメラメーカーは今、大きな岐路に立たされている。二つの壁をぶち破らなければカメラは死ぬ。通信と頭脳だ。今後、写真撮影の本質的な機能にこの二つは欠かせないものになる。スタンドアロンでしか動かず処理能力の限られたCPUしか積めなければ、カメラの未来はない。両手を縛られて戦えば、負けるのは当たり前だ。 カメラには、写真を撮影するという機能に加え、機械としての魅力がある。持っているだけで気分が上がり、いい写真が撮れるような気がする、という不思議な魅力だ。私は、機械としてのカメラが好きだ。気に入ったカメラで写真を撮るという行動も好きだし、写真そのものも好きだ。気に入ったカメラで写真を撮っているときの高揚感と楽しさは、スマホでは味わえない。だからこそカメラには生き残ってほしい。切に願う。「スマホで撮れば良かった」とは言われたくない。カメラメーカーの奮起に期待したい。(BCN・道越一郎)